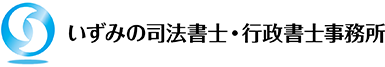相続登記の義務化の施行期日が決定
2021.12.30更新
令和3年4月28日、相続による不動産の名義変更(相続登記)の義務化に関する改正法が公布されました。そして、令和3年12月14日に本改正法の施行期日が決定しました。
相続登記の申請義務化に関する改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
今回の法改正により、今まで義務ではなかった相続登記が義務化されることになります。
なお、遺産分割協議が期間内に整わない等の事情により、相続登記ができない場合の簡易な義務履行手段もあわせて創設されます。以下で制度の概要をご紹介します。
1.相続登記の義務化の内容
不動産の所有者(登記名義人)が亡くなったときは、当該不動産の権利(所有権)を取得した相続人は、 自己のために相続があったことを知り 、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
なお、「法定相続分による登記」又は、後に説明する「相続人申告登記」を申請した場合には申請義務を履行したものとみなされます。
相続登記を申請すべき義務がある者、要するに、相続や遺贈により不動産を取得した相続人が、「正当な理由がないのにその申請を怠ったとき」は、10万円以下の過料に処されます。
「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化されるそうです。
2.改正法施行前の相続も対象になる?
改正法施行後に相続が発生した場合、自己のために相続があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
では、改正法の「施行前」に発生した相続も対象になるのでしょうか。
改正法施行前に相続が発生した場合には、以下の取り扱いになります。
①自己のために相続があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日。
②改正法施行日(令和6年4月1日)
①または②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
| まとめると以下のとおりです。 ○ 施行日前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課される。 ○ 申請義務の履行期間については、施行前からスタートしないように配慮。 具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートする。 |
3.相続人申告登記の新設
相続人申告登記とは、①不動産の所有者(登記名義人)が亡くなった旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、その申請義務を履行したものとみなされる制度です。ただし、あくまでも登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになりますので注意を要します。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。これにより、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になり、所有者を容易に特定することが可能となります。
| ▶ 相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)。 ▶ 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定は不要。 |
添付書面も簡易なものとなり、資料収集の負担が軽減されるそうです。
4.遺産分割成立時の追加的義務
繰り返しになりますが、「相続や遺贈により不動産を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすること」が基本的義務となります。
改正法ではあわせて追加的義務として遺産分割が成立した場合、その内容を踏まえた登記申請をすることも義務付けています。相続人がすべき登記申請の内容は以下のとおりです。
|
【3年以内に遺産分割が成立しなかったケース】
【3年以内に遺産分割が成立したケース】
【遺言書があったケース】 |
4.最後に
相続登記の義務化とあわせて登記簿の住所に変更があった場合の住所変更登記も義務化されることになっています(施行期日は未定)。相続登記の義務化については、施行日前に生じた相続も対象となりますので、登記手続が未了の場合には、お早めに手続されることをお勧めします。相続登記の手続については司法書士等の専門化にご相談ください。